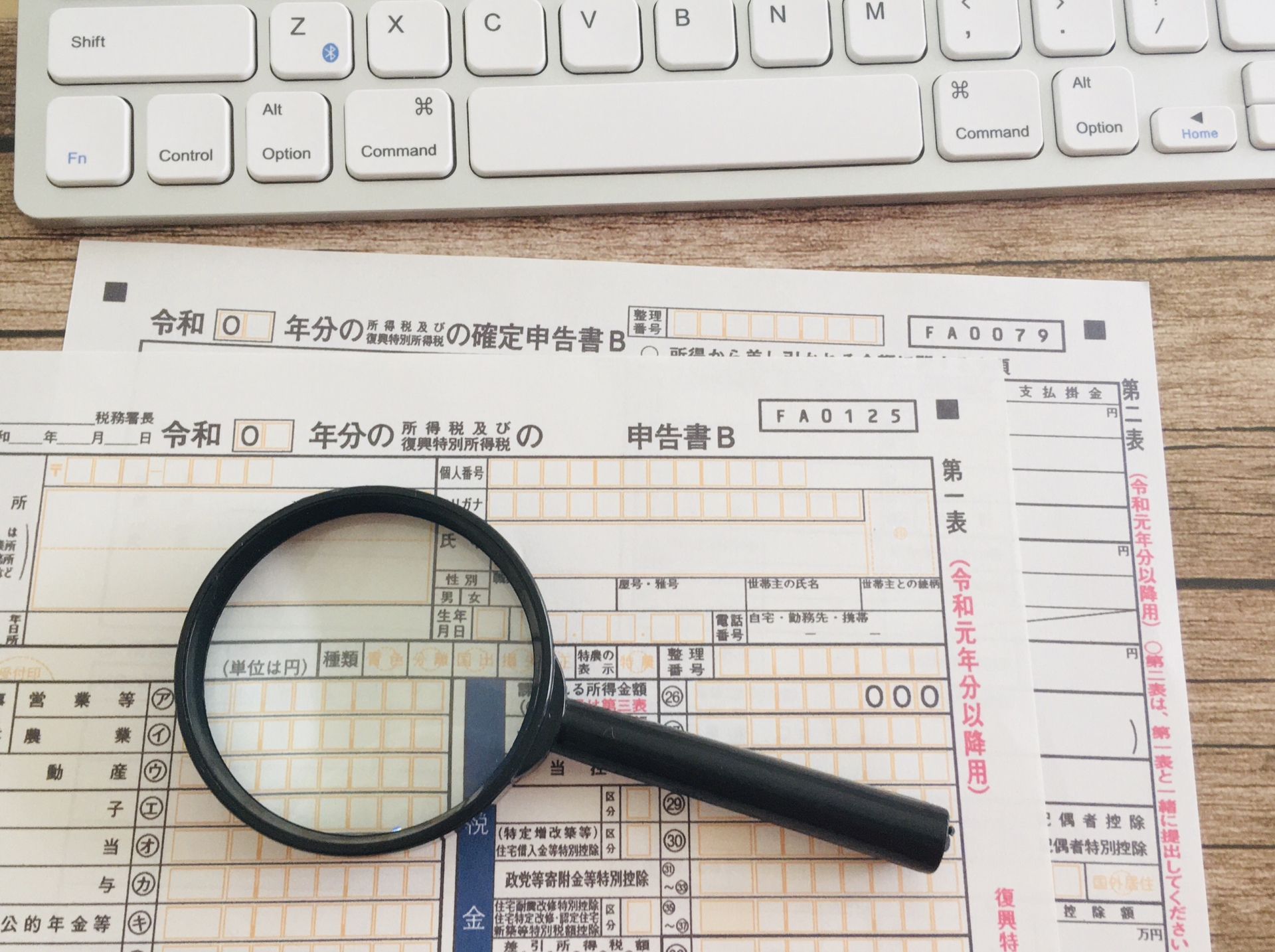
電子帳簿保存法が2022年1月に改正され、税務書類の電子保存が容易になった一方、電子保存の義務化で業務の見直しが必要になります。
しかし、企業の対応は十分とは言えない状況です。義務化が2年先送りされた今のうちに、電子帳票システムや会計システムを見直すなどしましょう。
▼ 目次
電子帳簿保存法の概要
電子帳簿保存法とは、企業が扱う請求書や領収書などの税務書類について、デジタルデータとして書類を保存することを認めた法律です。
その電帳法が2022年1月に改正され、書類を電子保存する際の要件が大きく変わりました。
①電子保存が容易に
変更点には、まず要件の緩和があります。
改正前は、紙の請求書などをスキャナーで読み取って電子保存する場合、税務署長の事前承認が必要でした。
この承認制度は改正で廃止され、要件を満たす会計システムを使っていれば承認を得ず電子保存が可能になりました。
また、電子保存した日時を証明するタイムスタンプも、付与要件が緩和されました。
付与期限が最長2か月以内に延長されたうえ、「修正・削除の記録が残るクラウドサービスの利用でタイムスタンプ不要」になりました。
2022年1月の改正により、電子データ保存にともなう作業の負荷は、軽減されたと言えるでしょう。
②紙の書類が認められないケースも
2022年1月の改正により緩和された部分がある一方で厳格化された部分もあります。
改正によって、電子データで受け取った書類の電子保存が義務化されました。
つまり電子データを紙に印刷したものは、正式な書類として認められなくなります。
電子データで受け取った領収書や請求書を印刷して経理部門に提出する という手順で処理をしていた企業も少なくないかと思いますが、改正後はそのような処理がおこなえなくなります。
こちらに違反すると、青色申告の対象外なる恐れがあり、納税額の増加につながることを考えると小規模な事業者にとって大きな問題です。
また、電子帳簿保存に対応できていないから、と今までの得意先から取引を断られるケースも考えられます。
これらを考えると、電子帳簿保存法の改正には全企業が対応する必要があると言えるでしょう。
電子保存義務化は2年先送り
電子保存義務化に対しては、中小企業をはじめ多くの企業から戸惑いの声が上がりました。
新たな会計システムの導入や、会計業務の大幅な見直しが必要なとなり、現場での負担がとても大きいからです。
企業の対応が滞っていることから、国税庁は「適切に記帳されていれば紙保存を容認する」と、対応への猶予として2年の期間(2022年1月1日から2023年12月31日)を設けました。
ただし、電子保存の義務化は2年先送りされただけであり、令和6年(2024年)1月より適用される予定です。
企業の対応状況は?
8割以上が不十分
2022年6月に行われた調査では下記のような結果が得られました。
まず改正電子帳簿保存法について理解している人は57.8%で、42.2%が理解をできていませんせした。
また、請求書や領収書以外への電帳法対応状況を尋ねたところ、
「既に対応済み」(17.9%)
「現在対応中」 (23.8%)
「対応方法を検討中」(19.9%)
「まだ対応していない」(38.5%)
という結果になり、8割以上が対応不十分という状態です。
半数は対応方法未定
改正電子帳簿保存法の対応方法については、下記のような回答が得られました。
「クラウドのサービスを利用する」(24.3%)
「今使用している既存のシステムを利用する」(21.8%)
「自社で新たにシステムを構築する」(6.1%)
大きな問題は「未定/不明」という回答が47.8%もあったことです。
すでに改正内容に関する情報は得やすくなっていますし、会計システムなどベンダーもほとんどが対応済み、もしくは対応方針を公表済みでしょう。
しかしながら、この時点企業がで対応できていない、対応方法を決めていないということは、ベンダーからの積極的な働きかけが必要なのかもしれません。
対応していない理由は?
担当者不足、知識不足
改正電帳法に対応できていない企業で経理や財務、人事、総務を担当している人に対しておこなった調査によると、
未対応の理由は以下のとおりで、担当者不足、知識不足が目立ちました。
「システムが導入されていない」(41.2%)
「運用を整備する担当者がいない」(31.6%)
「社内で改正電子帳簿保存法を理解できている人が少ない」(31.0%)
「自社内に電子データに関するノウハウがない」(24.5%)
まとめ
企業にとって「改正電子帳簿保存法に対応しない」という選択肢はあり得ません。
ペーパーレスや押印廃止の流れから電子契約は確実に増えていく、当たり前になっていくことを考えると電子保存の義務化には、必ず対応する必要があります。
電子帳票システムや経費精算システム、クラウド会計ソフトなど関連製品の対応も進んでいる中で、
電帳法へ対応していることを示す日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)認証も参考になります。このような情報をもとに改正電帳法へ対応を進めていきましょう。
また、こうしたシステムを販売しているベンダーの資料を取り寄せたり、セミナーに参加したりするなどして、まずは情報を集めることから始めてみるのはいかがでしょうか。




